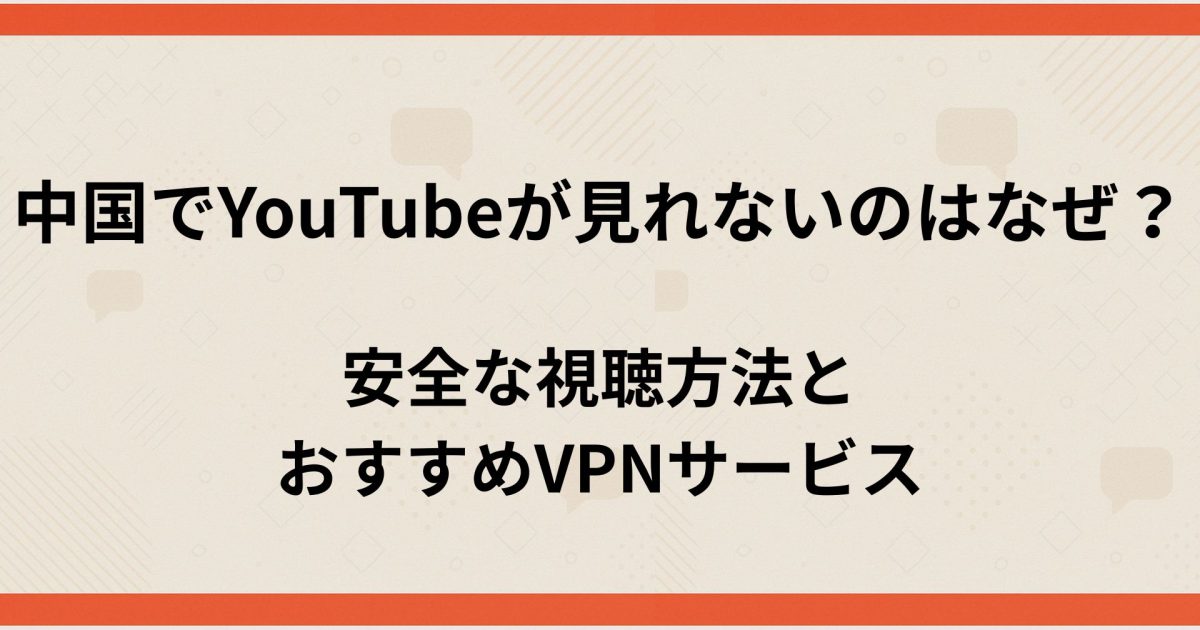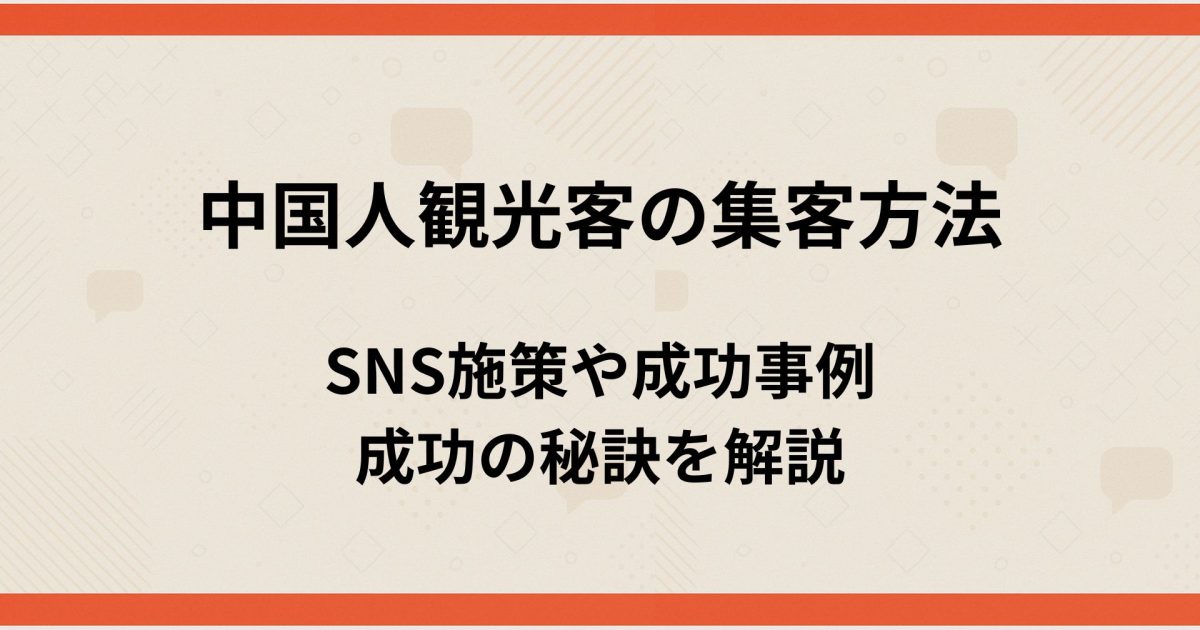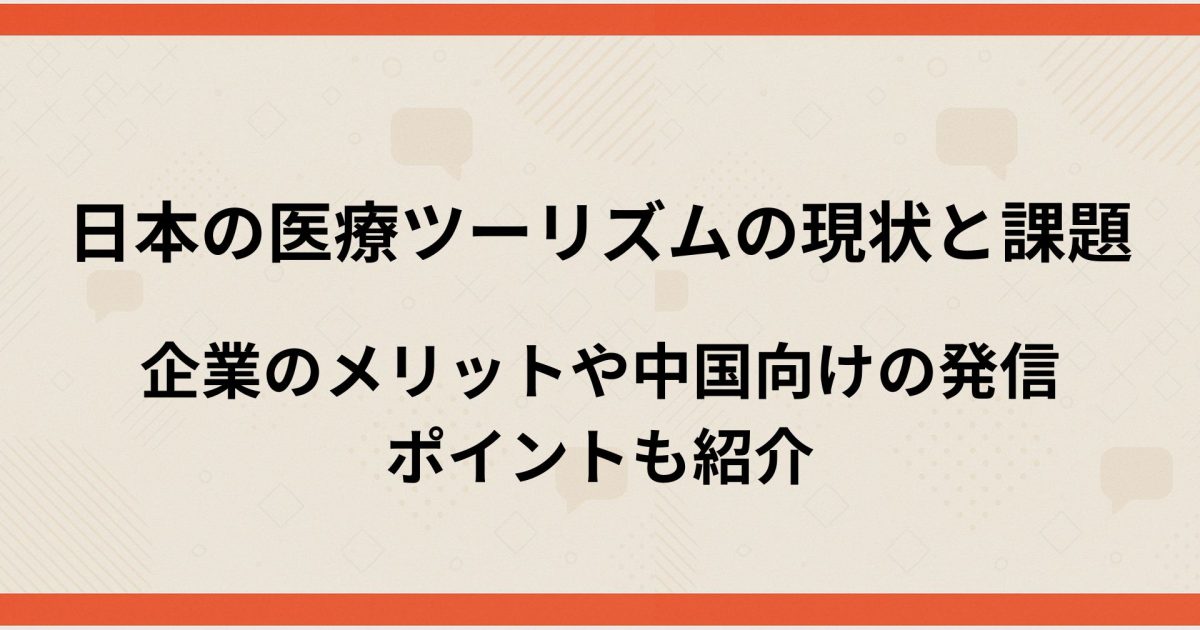「中国インバウンド集客に取り組みたいが、効果的な手法が見つからない」
「中国人観光客の集客を成功させたいけど、どうアプローチすればいいか分からない」
そのように悩んでいる企業担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、中国人観光客の最新動向や特徴、SNSを活用した成功事例、インバウンド施策のポイントを、データと実例を交えながらわかりやすく解説します。
2025年の最新トレンドも踏まえ、今後のプロモーション戦略にどう反映すべきかを解説するため、マーケティング施策を実施する際に役立つ内容です。
なお、弊社では中国SNSの運用代行を行っています。インバウンド集客に最適なSNSのご提案から中国人消費者たちのニーズに基づいた投稿コンテンツの作成、顧客管理対応まで中国ビジネスを一気通貫でサポートします。
お気軽にお問い合わせください。
【相談無料】中国SNSマーケティングなら東京マンダリンアワードに相談を
中国インバウンドの現状

中国人観光客は、現在のインバウンド市場で影響力のある訪日客層の一つです。
コロナ禍を経て訪日客数は大きく減少しましたが、近年は回復基調にあり、今後の動向に注目が集まっています。
この章では、中国インバウンド市場の現状を以下の6つの視点から整理し、今後の施策検討に必要な前提知識を提供します。
- 訪日中国人観光客数と推移
- 一人あたりの消費額
- 平均観光日数
- 地域別の訪問傾向と人気エリア
- 訪問する時期
- 中国人観光客の属性・価値観
各データや傾向を把握することで、中国人観光客へのアプローチ方法や訴求ポイントをより的確に判断できるようになるでしょう。
1.訪日中国人観光客数と推移
訪日中国人観光客数は、2023年以降回復傾向を見せています。2024年では約698万人に達し、パンデミック前の水準へ徐々に近づいてきています。
さらに2025年の1〜7月には約569万人が訪日するなど、コロナ以前の同時期を上回る勢いで回復してきました。このペースが継続すれば、2025年の年間総数は2019年(約960万人)に迫る可能性があります。
特に注目すべきは2025年6月単月の数字で、訪日中国人は約79万8,000人と前年より約20%増加し、1〜6月累計では約471万8,000人に達しています。これは、2019年上半期の約453万人を上回る水準です。
この回復傾向は、航空路線の再開やビザ緩和などの受け入れ環境の改善によって後押しされています。
こうした状況を踏まえると、日本の中国インバウンド市場は今後さらに拡大する可能性が高いと考えられます。
出典:日本政府観光局「訪日外客数(2025 年 6 月推計値)」
出典:日本政府観光局「2025年 訪日外客数(総数)」
2.一人あたりの消費額
2023年に訪日した中国人観光客の一人あたり旅行支出は約32万円に達し、2019年比で50.4%増と大きく増加しました。
以下に費目ごとの一人あたりの消費額をまとめました。
| 順位 | 費目 | 購入率 | 購入金額 |
| 1位 | 菓子類 | 72.7% | 13,258円 |
| 2位 | 化粧品・香水 | 52.2% | 44,995円 |
| 3位 | 医薬品 | 36.9% | 21,922円 |
| 4位 | 衣類 | 36% | 47,926円 |
| 5位 | その他食料品、飲料、たばこ | 34.1% | 15,688円 |
| 6位 | 靴、鞄、革製品 | 28.2% | 101,933円 |
| 7位 | 健康グッズ・トイレタリー | 15.9% | 23,820円 |
| 8位 | 酒類 | 12.0% | 18,437円 |
| 9位 | 電気製品 | 10.7% | 50,778円 |
| 10位 | 民芸品・伝統工芸品 | 5.5% | 15,823円 |
参考:国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向」
支出の内訳をみると、菓子類(72.7%)、化粧品・香水(52.2%)、医薬品(36.9%)などの消耗品の購入率が特に高く、中国人観光客にとって定番のお土産となっています。
靴・鞄・革製品は購入率こそ28.2%にとどまるものの、一人あたりの平均購入額が約101,933円と高く、支出全体を押し上げる要因になっています。
3.平均観光日数
滞在日数は2019年の5.8泊から、2023年には16.2泊と倍以上に増加しました。これは短期的な観光旅行から長期滞在型の旅行スタイルへシフトしていることを示しています。
航空券やビザ取得にかかる費用対効果を重視し、一度の訪問で多様な体験を満喫したいという意識の高まりがあります。
加えて、地方都市への訪問数の増加や文化体験の広がりも、旅行日数の長期化に寄与しています。
このような傾向を踏まえると、観光事業者には短期滞在者向けのサービスに加え、長期滞在者に適したキッチン付きホテルや民泊での「自炊型プラン」や体験型コンテンツの整備が求められるでしょう。
出典:国土交通省観光庁「訪日外国人の消費動向」
4.地域別の訪問傾向と人気エリア
訪日中国人観光客は東京・大阪・京都などの都市部を中心に訪問しますが、地方エリアへの関心も高まっています。
以下に、2024年の地域別の訪問傾向をまとめました。
| 都道府県 | 訪問率(%) |
| 大阪府 | 53.9 |
| 東京都 | 53.2 |
| 京都府 | 37.5 |
| 千葉県 | 36.6 |
| 奈良県 | 14.4 |
出典:日本政府観光局 日本の観光統計データ「2024年 都道府県別訪問率ランキング(中国・全体)」
また、2024年1月~2024年12月の中国の「日本の都道府県」検索数を以下の表にまとめました。
| 都道府県名 | 検索数 |
| 東京 | 61,900 |
| 大阪 | 40,000 |
| 京都 | 36,700 |
| 北海道 | 22,600 |
| 奈良 | 20,900 |
| 沖縄 | 12,100 |
| 福岡 | 11,480 |
| 和歌山 | 10,860 |
| 熊本 | 10,360 |
| 青森 | 6,200 |
参考:アウンコンサルティング株式会社「47都道府県に関する年間検索トレンド(中国編)」
検索データでは、都市部に加えて北海道や沖縄など自然やリゾート要素の強い地域、さらには奈良・和歌山・熊本・青森などの文化体験や地方資源のある地域にも関心が集まっていることがわかります。
このように、実際の訪問傾向では都市部が中心な一方、検索トレンドからは「都市+地方」を組み合わせた複合的なニーズが浮かび上がっています。今後は、主要都市を起点に地方へ足を伸ばせるような観光戦略が効果的になるでしょう。
5.訪問する時期
訪日中国人の旅行時期は主に「春節(旧正月)」「労働節(5月)」「国慶節(10月)」の3つの大型連休と学生の夏休み(7〜8月)に集中します。この時期は観光地や小売業で需要が急増するため、事前の準備が欠かせません。
たとえば2023年の国慶節では、10月度の売上高は、大丸松坂屋百貨店合計で前年同月比14.3%増、関係百貨店を含めた百貨店事業全体でも13.6%増となりました。この背景には、国慶節をはじめとする大型連休に合わせて訪日観光客が増加したことが挙げられます。
大型連休のタイミングでは、訪日客の需要が一気に高まるため、あらかじめ商品ラインナップの強化や販促キャンペーンの準備を行うことが成果に直結します。
参考:PR TIMES「中国人観光客が「日本旅行」を選ぶ理由と最新トレンド」
出典:J.フロント リテイリング株式会社「2023年10月度 J.フロント リテイリング 百貨店事業 売上速報」
6.中国人観光客の属性・価値観
2024年のデータによると、訪日中国人観光客の中心層は20〜40代で、男女比は男性が約43%、女性約57%でした。旅行の目的は「ショッピング」「観光地巡り」「体験型アクティビティ」など多岐にわたります。
なかでも若年層は、小紅書やWeChatなどを活用し、旅行中の体験や購入品をSNSに投稿する傾向が強く、いわゆる「映える」体験やスポットに高い関心を寄せています。
一方で、家族連れやシニア層は、安全性や快適さ、利便性を重視する傾向が強く、施設やサービスの質が選定基準になります。
このように属性ごとに価値観や行動特性が異なるため、プロモーションでは一律の訴求ではなく、ターゲット別にニーズをとらえた戦略設計が不可欠です。
出典:日本政府観光局「訪日外国人の消費動向 2024年 年次報告書」
【最新版】中国インバウンドにおける観光客の消費・行動傾向

これまで見てきた訪日中国人観光客の動向を踏まえると、近年の消費・行動には明確な変化が見られます。
特に以下の4つの傾向は、中国インバウンド戦略を考える上で押さえておくべき重要な視点です。
- 買い物は品質重視に変化している
- コト消費への関心が高まっている
- 体験を重視している
- 旅行スタイルが多様化している
それぞれ詳しく解説します。
1.買い物は品質重視に変化している
かつて「爆買い」で知られた中国人観光客ですが、現在は品質を重視する買い物へとシフトしています。経済成長にともない高品質で安全な商品を求める意識が強まりました。
主に日本製の化粧品や健康食品が信頼できる商品として人気を集めています。百貨店の売れ筋も高単価の革製品や最新家電に移っています。
そのため今後の中国インバウンド対策は、価格訴求ではなく品質を前面に出すことで成果につながるでしょう。
2.コト消費への関心が高まっている
中国人観光客は、物を買うだけでなく体験そのものに価値を見出すようになっています。和菓子作りや茶道、温泉宿泊などの「コト消費」が人気を集めるのはそのためです。
背景には「特別な体験をSNSでシェアしたい」という文化があり、体験型観光は購買意欲の刺激にも直結しています。
国土交通省によると「娯楽等サービス費」の中で中国人観光客の支出割合が最も高かったのはテーマパークでした。さらに、訪日旅行におけるサービス支出では「美術館・博物館」「現地ツアー・観光ガイド」「温泉施設」などの体験型サービスの利用率が、いずれも2019年より増加しています。
3.体験を重視している
近年、訪日中国人観光客の間では「どのような体験ができたか」を旅行の満足度の基準とする傾向が強まっています。
たとえば若年層には、自然の絶景での撮影などの体験が人気です。一方でファミリー層には、子ども向けのアクティビティや安全性の高い宿泊施設が選ばれやすくなっています。
北海道での雪遊びや、沖縄でのマリンアクティビティは、多様なニーズに応える例であり、世代を問わず高い評価を得ています。
このように、旅行自体が“体験価値を得る場”としてとらえられます。したがって、マーケティング施策を実施する際は単なる観光地の紹介にとどまらず、滞在中にできる体験を訴求しましょう。
4.旅行スタイルが多様化している
かつて団体旅行が中心だった中国人観光客の旅行スタイルは、近年では個人旅行(FIT)やフリープラン型の旅へと大きくシフトしています。
背景には、SNSを活用してリアルタイムに観光情報を収集できるようになり、旅行プランの自由度が増した点が挙げられます。
さらに、Trip.comやCtripなどのオンライン予約サービスの普及により、航空券や宿泊施設の手配が簡単かつ低コストで行えるようになったことも理由の一つです。
また、2025年以降は、中国人観光客の訪問先は大都市にとどまらず、地方へも広がりを見せています。背景には、以下のように訪日環境の整備が進んでいることがあります。
- 観光庁による地方誘客政策の推進
- 多言語対応の強化
- 中国各地と地方空港を結ぶ直行便の増加など
特に東北・四国・九州などの都市圏外の地域では、追い風を受けて中国人観光客の来訪が増加しています。
このように、今後は団体・個人の両方のニーズに応えつつ、地方観光を取り込む柔軟な戦略が重要になるでしょう。
中国インバウンドプロモーションの4つの戦略

中国インバウンドプロモーションを成功させるには「どこで情報を届け、どう購買行動につなげるか」を意識した戦略設計が欠かせません。
特に中国市場では、日本と異なる情報流通経路や価値観を踏まえた対応が必要です。
本章では、中国インバウンドプロモーションを成功させるための4つの戦略を紹介します。
- 小紅書・WeChatなどの中国のSNSを活用する
- KOLを起用する
- 中国の祝日に合わせた施策を実施する
- 品質の高さをアピールする
それぞれの戦略の成功ポイントを具体的に解説します。
1.小紅書・WeChatなどの中国のSNSを活用する
中国で効果的にインバウンド集客を行うには、現地で主流のSNS活用が不可欠です。
なぜなら、中国ではInstagramやGoogleなどの日本で一般的なサービスが利用できないため、日本企業が普段使うチャネルでは情報が届きにくいからです。
代わりに、中国では小紅書(RED Note)やWeChatなどのSNSが主流です。小紅書は旅行先での体験や買い物のレビューが多く投稿される口コミ型SNSで、訪日前の情報収集に活用されています。
一方、WeChatはチャット機能に加え、企業アカウントを通じた情報発信機能や予約・決済機能も備えており、日常生活に欠かせないツールです。旅行中の情報検索や問い合わせ、買い物時の決済に至るまで活用できます。
このように、現地SNSの活用が、中国インバウンド施策の成果を大きく左右します。
2.KOLを起用する
中国インバウンド施策では、KOL(キーオピニオンリーダー=影響力のあるインフルエンサー)の活用が有効です。彼らの発信は「訪日したい」「実際に日本に行こう」という動機付けに直結します。
たとえば、草津温泉は、中国のDouyin(抖音)で人気を集める旅系KOLを起用し、訪日旅の情報発信を行いました。投稿の中では、東京から草津へのアクセス方法や宿泊予約の詳細なども紹介され、数千のシェアを獲得するなど高い拡散効果を発揮しました。これにより、集客にもつながっています。
このように、KOLの影響力は単なる宣伝を超え、実際の訪問行動にまでつながります。さらに、KOLの発信に加えて一般ユーザーの口コミやレビューも効果的で、組み合わせることで相乗効果が期待できるでしょう。
参考:Douyin(抖音)「我叫咩直」
3.中国の祝日に合わせた施策を実施する
訪日中国人観光客の旅行時期は、春節(旧正月)・国慶節(建国記念日)・夏休みなどの大型連休に集中する傾向があります。
| 春節(旧正月) | 旧暦の1月1日から始まる8連休(毎年日付が変動。2025年は1月28日〜2月4日) |
| 国慶節(建国記念日) | 10月1日を含む8連休(いわゆる「ゴールデンウィーク」) |
| 夏休み | 学校の休暇は7月上旬〜8月末まで |
これらの時期は中国全土が旅行モードに入るため、訪日需要も一気に高まります。したがって、これらの祝日に合わせたターゲット施策を展開することで、高い集客効果が期待できます。
たとえば、表参道エリアで実施された「Tokyo Shopping Week 春節版」では、以下のような施策が行われました。
- 多言語対応のストリートフラッグの掲出
- 中国語対応スタッフによる道案内
- 購入者限定の抽選キャンペーン
このように、祝祭のタイミングに合わせた施策では「訪日旅行を快適に楽しめる環境」が用意されていることを明確に伝えることが重要です。
4.品質の高さをアピールする
中国人観光客の多くは、価格よりも品質を重視する傾向があるため、高品質であることのアピールが求められます。
特に医薬品や食品、化粧品などでは、現地の文化や法規制に対応した表示や認証の有無が、購入の判断材料になります。近年では、健康志向や宗教的配慮、環境意識の高まりを背景に「ハラール認証」「オーガニック認証」「エコ認証」など、価値観に合った製品表示が求められるようになっています。
また、中国語での説明表記や使用方法の案内、実績の明示など、信頼を得る工夫も欠かせません。単に「高品質」と伝えるだけでなく、根拠や安心材料を示すことで、購買行動につながりやすくなります。
中国インバウンドプロモーションの企業事例|SNSを活用した事例を2つ紹介

中国人観光客の多くは、訪日前に小紅書(RED Note)やWeiboなどのSNSで旅行情報を収集しています。そのため、SNSを活用したプロモーションは、中国インバウンド施策で欠かせない手段です。
- 動画訴求により集客に成功したスギ薬局|小紅書(RED Note)
- 北海道写真コンテストにより地域全体での集客に成功|Weibo
ここでは、小売業と地域観光それぞれの成功事例を紹介し、具体的な取り組み内容と成果を見ていきます。
1.動画訴求により集客に成功したスギ薬局|小紅書(RED Note)
スギ薬局は、小紅書(REDNote)の公式アカウントを動画中心に運用し、宣伝だけではなく旅行者が本当に役立つ情報発信で成果を上げています。
訪日中の困りごと解決や買い物のコツに寄り添った内容が支持され、いいねや保存(ブックマーク)を安定的に獲得してきました。
さらに2025年にはフォロワー数が10万人を突破し、中国インバウンド集客の成功事例として注目されています。
参考:小紅書「杉药局」
2.北海道写真コンテストにより地域全体での集客施策を実施|Weibo
北海道観光局は中国のSNS「Weibo」を活用し、北海道写真コンテストを開催しました。観光客や地元住民が撮影した写真を投稿する形式で、参加者自身が北海道の魅力を発信し、観光客の増加を狙いました。
SNSを活用した観光施策は、企業単位の集客にとどまらず、地域全体の観光振興にも有効です。
参考:PRTIMES「北海道観光機構の中国向けSNS 「Weibo」で、北海道観光の魅力を写真でシェアする『北海道旅行写真コンテスト』を開催!」
中国インバウンド施策で成果を上げるために意識したい2つのポイント

中国インバウンド施策を実施するには、複数の要素に配慮する必要があります。
ここでは、現場での対応力を高め、施策の成果を安定して得るために意識すべき2つの重要な視点を紹介します。
- 決済・予約・問い合わせの導線は「中国仕様」に最適化する
- 国際情勢や政策変動による変化リスクにも備える
以下の項で詳しく解説します。
1.決済・予約・問い合わせの導線は「中国仕様」に最適化する
訪日中国人観光客にとって「使い慣れた方法でスムーズに支払い・予約・問い合わせができるかどうか」は、サービス利用の可否を左右する重要な判断基準です。
たとえば、中国ではAlipayやWeChat Payなどのモバイル決済が主流であり、現地と同じ決済環境を提供できるかが購買意欲に直結します。実際に富良野市では、WeChat公式アカウントやミニプログラムを活用して宿泊予約・観光情報・オンライン決済を一体化しました。現地での情報収集や手続きが簡単になり、利便性向上に貢献しています。
また、問い合わせ対応を中国語で行うことも、心理的ハードルを下げ、利用促進につながります。こうした「中国仕様」の導線整備は、集客の前提となる基盤です。
「中国仕様」の決済導入の問い合わせは、東京マンダリンアワードへ
参考:やまとごころ.jp「富良野市が一丸となって取り組む「WeChat」から始まる観光のデジタルエコシステム」
2.国際情勢や政策変動による変化リスクにも備える
中国インバウンド市場は、国際政治の緊張、経済制裁、ビザ発給の制限、感染症拡大など、外部要因による影響を強く受けるリスクが高い市場です。
実際、コロナ禍では渡航制限により訪日観光が事実上ストップし、多くの企業が売上減に直面しました。外交的な関係悪化や輸出規制の強化なども、今後同様の影響をもたらす可能性があります。
こうした不確実性に備えるためには、訪日集客だけに依存しない戦略が不可欠です。
たとえば、コロナ禍中には中国国内の需要を狙った越境EC(国境を越えてオンラインで商品やサービスを売買すること)への切り替えが有効に機能しました。2023年の日本から中国への越境EC輸出額は約2兆4,301億円(前年比7.7%増)に達したという調査結果もあります。
今後のインバウンド施策では、現地での購買チャネルやSNSを通じた接点を維持しつつ、有事にも耐えられる柔軟な体制を整えることが求められます。
出典:経済産業省 令和4年度電子商取引に関する市場調査 報告書
出典:経済産業省 令和5年度電子商取引に関する市場調査 報告書
2025年の中国インバウンドトレンド・今後の見通し

2025年以降、中国インバウンドは再び大きな成長局面を迎えると予想されます。特に、観光スタイルの多様化や体験重視の傾向がより顕著になっています。
ここでは注目すべき2つのトレンドを紹介します。
- 大阪・関西万博による需要増加
- アウトドアへの注目
本章を読んで、自社の集客戦略に役立ててください。
1.大阪・関西万博による需要増加
大阪・関西万博では、約2,820万人の来場者が見込まれており、そのうち約350万人(12%)が海外からの訪問客と想定されています(2025年8月記述)。特に中国からの訪日需要は高く、今後のインバウンド市場をけん引する存在になるでしょう。
また、万博による訪問動機は大阪だけにとどまらず、近隣の京都・奈良・神戸などの関西圏全体の観光にも波及効果が及ぶと考えられています。これにより、中国人観光客の滞在期間や消費単価の増加も期待されます。
出典:EXPO2025「大阪・関西万博 来場者輸送具体方針(アクションプラン)」
2.アウトドアへの注目
中国国内でアウトドア志向が一段と高まっており、その影響は訪日旅行にも反映されています。実際に、SNSでは「ハイキング」関連の投稿が活発です。
たとえば、douyin(抖音)では80億回以上の閲覧数、小紅書(REDNote)には353万件以上のハイキング関連投稿が確認されています。
近年は地方観光へのニーズも高まっており、こうしたアウトドア体験は都市部では得られない魅力として注目されています。
地方エリアでは、体験型コンテンツを通じて滞在時間や消費額の増加も期待できるため、今後のインバウンド戦略で有効な切り口となるでしょう。
中国インバウンド対策ならSNS集客が可能な東京マンダリンアワードに相談を

中国インバウンド市場は、コロナ禍を経て確実に回復傾向にあります。実際、2024年の訪日中国人観光客数は約698万人に達し、一人あたりの消費額も2019年比で約1.5倍に増加しています。
こうした背景を踏まえ、中国インバウンド戦略では、小紅書やWeChatなど中国独自のSNS活用や、KOL(キーオピニオンリーダー)による影響力のある発信が欠かせません。
しかし、中国インバウンド対策を効果的に行うには、現地プラットフォームへの理解や文化的背景、モバイル決済への対応など、専門的な知見が求められます。
東京マンダリンアワードでは、小紅書・WeChat・Weiboなどの現地SNSの運用代行から、KOL施策、プロモーション企画までワンストップで対応可能です。
自社内での対応に限界を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の中国インバウンド施策を成果に導くための、最適な戦略設計と実行支援をご提案いたします。