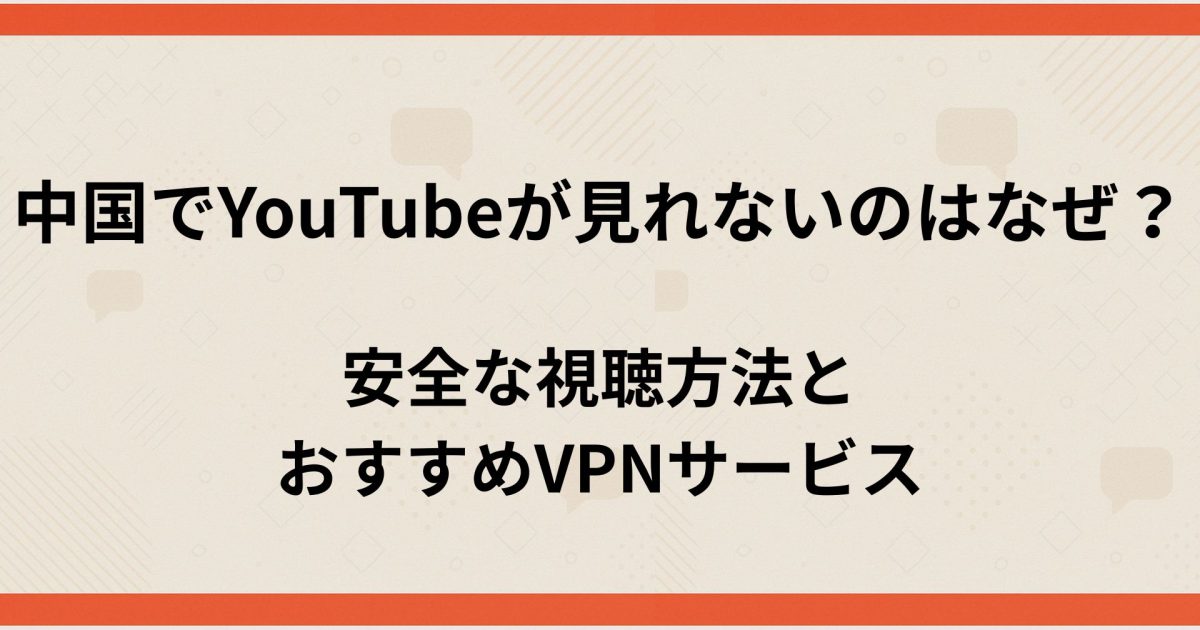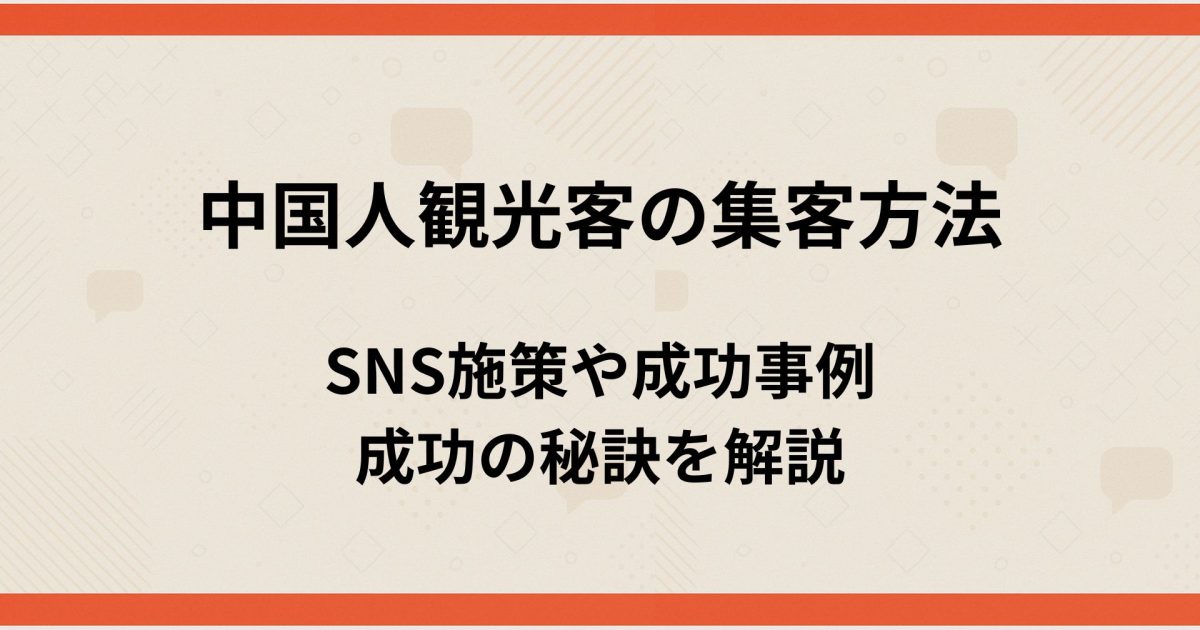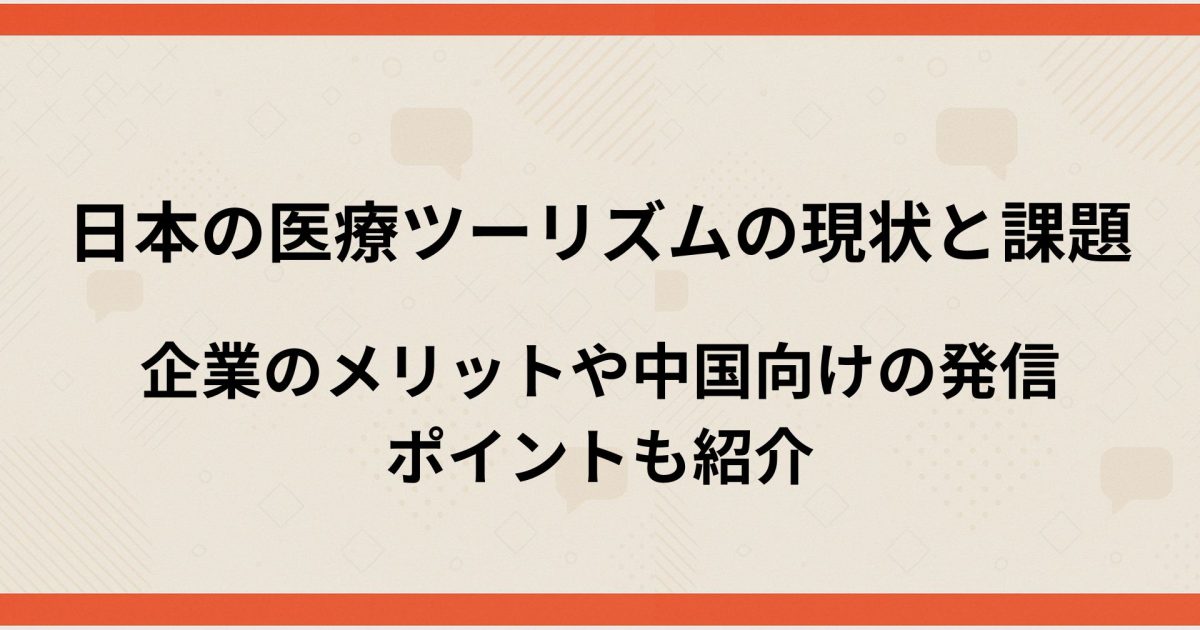「自社のサービスを医療ツーリズム市場にどう展開すればよいか分からない」
「海外富裕層がどんな視点で日本の医療を選んでいるのかを知りたい」
「中国向けに医療ツーリズムのPRを始めたいが、何から手をつけるべきかわからない」
「医療ツーリズム」という言葉を耳にしたことはあっても、上記のような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
医療と観光を組み合わせた医療ツーリズムは、世界的に注目される産業の一つです。特に高い医療技術と安全性を誇る日本は、アジア圏を中心に選ばれる国となりつつあります。
そこで本記事では、日本における医療ツーリズムの定義や現状、世界との比較、企業が得られるメリットや課題・問題点などを詳しく解説します。
本記事を通して、日本の医療ツーリズムの可能性を理解し、集客戦略の立案に役立ててください。
中国向けに医療ツーリズムを展開したい企業には「東京マンダリンアワード」の活用がおすすめです。中国SNS運用の専門家が、アカウント設計からコンテンツ制作までを一気通貫で支援し、最短で成果を目指せる施策をご提案いたします。
無料相談も可能ですので、以下のリンクからサービス概要をチェックしてみてください。
【相談無料】中国SNSで医療ツーリズムの情報を発信するなら東京マンダリンアワード
日本における医療ツーリズムとは

日本における医療ツーリズムとは、海外の人が医療サービスを受けることを目的に日本へ渡航することです。
本章では、医療ツーリズムの定義・範囲や日本の医療が選ばれる理由を解説します。
医療ツーリズムの定義と範囲
医療ツーリズム(Medical Tourism)とは、健康診断や治療を目的として、自国を離れ海外で医療サービスを受ける観光活動のことです。受診先の医療水準や費用、滞在環境などを比較し、より良い医療体験を求めて国境を越える動きは、世界的に広がっています。
医療ツーリズムの対象範囲は広く、以下のような分野に分かれます。
| 分野 | 内容 |
| 予防・早期発見 | 健診・検診・人間ドックなど、健康維持や疾患の早期発見を目的とした医療サービス |
| 高度な治療 | 手術・専門治療・がん治療・再生医療など、高度な技術を必要とする治療サービス |
| 美容・アンチエイジング | 美容整形・皮膚治療など、美と健康を重視したサービス |
| リハビリ | 術後ケアや回復期医療、医療滞在を含む長期型の療養プログラム |
| 医療+観光融合 | 医療受診後に温泉・観光・宿泊などを組み合わせたプログラム |
このように、医療ツーリズムは単なる治療にとどまらず、医療を通じて旅行に新しい価値をもたらす産業として進化しています。
こうした流れの中で、日本も医療ツーリズムの受け入れ先として注目を集めています。日本における医療ツーリズムとは、医療を受けることを目的に、海外から日本を訪れることです。
特に高度な医療技術や衛生管理、安全な医療環境などが評価されており、アジア諸国を中心に外国人患者からのニーズが高まっています。
さらに日本では、長期滞在型のウェルネス施設といった総合的な医療サービスが提供されており「医療+観光」の融合を図った独自のスタイルが拡大中です。これらの取り組みは、地域経済の活性化にもつながっています。
政府もこの流れを後押ししており、医療滞在査証(医療滞在ビザ)の導入、医療通訳サービスの提供など、外国人患者の受け入れ体制を支援しています。
参考:厚生労働省「『地域の医療・観光資源を活用した外国人受入れ推進のための調査・実証事業』のモデル実証事業地域を募集します。」
日本の医療が選ばれる理由
日本が医療ツーリズムの目的地として選ばれる理由は、複数の要素が高い水準で揃っているからです。
主な要素には、次のようなものが挙げられます。
| 要素 | 評価されている点 |
| 医療技術の高さ | 世界的にも評価される先端医療や専門治療の技術が確立している |
| 安全性と信頼性 | 感染症対策・医療設備・衛生管理が徹底され、清潔かつ安心できる医療環境が整っている |
| ホスピタリティ | 医療スタッフの対応が丁寧で思いやりがある |
| 費用面のバランス | 欧米諸国よりも、低価格で、高水準な医療を受けられる |
| 滞在の快適さ | 治療とリラクゼーション・おもてなしを組み合わせたプログラムが用意されているケースがあり、心身の回復を支える |
| 政府・自治体の支援 | 医療滞在ビザ制度の整備や受け入れ施設の認定など、行政の支援体制が充実している |
日本の医療は、世界トップレベルの治療技術と清潔で安心な受診環境の両方を備えている点が特徴です。
さらに、外国人患者は医療滞在中に、日本ならではの文化体験や自然に触れられる機会も多く、心身の回復をサポートする滞在が実現できます。
日本の医療ツーリズムの現状|世界と比較した日本の優位性

日本は、世界的に見ても高度な医療技術や安全性、きめ細やかなホスピタリティが評価されている国です。実際に、日本の医療を求めて来日する外国人は、治療の質だけでなく、医師やスタッフの丁寧な対応や施設の快適さにも高い満足度を示しています。
一方、世界では医療ツーリズム市場が急成長しています。2024年の世界市場規模は約1,009億ドル(約15兆5千億円※2025年11月時点)に達し、今後は年平均23.1%のペースで拡大する見込みです。
出典:Straits Research「医療観光市場 サイズと展望 2025-2033」
またアジア地域では、以下の国々が医療ツーリズム分野で主導的な地位を築いています。
| 国 | 特徴 |
| タイ | 国際認証(JCI)を取得した病院が多く、信頼性の高い先端医療を提供する |
| シンガポール | 整形外科、不妊治療、移植などの分野で高度なケアを提供 |
| 韓国 | 美容医療分野に強みがある |
これらの国々と比較すると、日本は制度の活用や受け入れ件数、国際的な情報発信の面では後れを取っているのが実情です。その背景として、医療滞在ビザの制度が十分に活用されておらず、実際の取得者数も年間約1,600人にとどまっています。
一方で、日本にはまだ大きな成長余地が残されており、医療機関や関連事業者にとっては今後の市場拡大に向けた好機と捉えることもできます。
医療の質、安心・清潔な環境、文化体験といった日本ならではの強みを活かせば、マーケティングに活かすことも可能です。
出典:e-Start「ビザ(査証)発給統計」
日本企業にとっての医療ツーリズムのメリット

日本企業にとって、医療ツーリズムは新たなビジネス機会を生み出す領域です。
まず、国内の医療機関のみならず、以下のような多様な業種が連携することで、付随サービス市場の成長も期待できます。
- 旅行業
- 宿泊業
- 通訳業
- コーディネート業など
例えば、三菱商事株式会社では検診・先端医療を活用した医療ツーリズム事業を国内で展開するために、検診施設を運営する企業と合弁検討を開始しています。
また、医療ツーリズムによる消費は医療費だけにとどまらず、宿泊・交通・観光といった周辺消費も伴うため、地域経済・関連産業にも波及効果が生まれます。
このように、医療ツーリズムは医療機関にとどまらず、旅行会社や宿泊施設、通訳サービス、観光事業者など多様な業種にビジネス機会をもたらします。
参考:三菱商事株式会社「メディカルツーリズム分野におけるリゾートトラストグループ・三菱商事による共同検討について」
日本の医療ツーリズムが抱える3つの課題や問題点

日本の医療ツーリズムは世界的にも高いポテンシャルを持つ一方で、受け入れ拡大に向けていくつかの課題や問題点を抱えています。
主なポイントは次の3つです。
- 情報発信が不足している
- 手続きや費用がわかりにくい
- 医療と観光の連携が不足している
以下でそれぞれ詳しく解説します。
課題・問題点①情報発信が不足している
日本は高度な医療技術と安全性を持っていますが、海外向けの情報発信には改善の余地があります。医療機関・行政・観光事業者が連携して行う国際プロモーション体制は行われているものの、十分に整っているとは言えません。
また、多言語対応のWebサイトやSNSなど、外国人が日本の医療サービスを理解・比較できる環境は限定的です。こうした課題があるため、国際的な競争力を高めるには情報発信の強化が不可欠です。
したがって、企業は医療機関や自治体と連携し、SNSやホームページなどを通じて、ターゲット国のユーザーに届く情報発信を支援する役割が求められます。
課題・問題点②手続きや費用がわかりにくい
次に挙げられるのが、ビザ申請や受診手続きの複雑さです。日本の「医療滞在ビザ」制度では申請時に「身元保証機関」を通して医療機関の受診予定証明書や保証書を取得する必要があり、外国人患者にとって大きなハードルとなっています。
参考:外務省「「医療滞在査証」の身元保証機関になられる方々へ」
さらに、診療予約や書類提出、支払い方法など、受診までの流れを一貫して理解できる仕組みが不十分である点も課題です。
加えて、日本の医療ツーリズムでは自由診療の扱いが多く、医療機関ごとに価格設定が異なるため、事前に総費用を把握しづらいという問題もあります。
こうした課題を解決するために、訪日外国人が日本の医療機関で受診できるよう、予約・通訳・医療滞在ビザのサポートを行っているサービスも展開されています。
課題・問題点③医療と観光の連携が不足している
医療ツーリズムにおけるもう一つの課題は、国内における医療と観光の連携体制が十分に整っていない点です。日本には、先進的な医療技術と豊かな観光資源がそろっていますが、それらを組み合わせた「医療滞在型プログラム」や「観光+医療サービス」のような商品開発は、まだ発展途上です。
したがって、自治体・観光事業者・医療機関が戦略的に連携し、患者にとって魅力的な滞在体験を提供できる体制を構築することが、今後の成長には不可欠です。
そのため、企業として医療ツーリズムを活用する際は、医療と観光を横断するサービスや商品を企画・提供することも検討しましょう。
【失敗しない】日本の医療ツーリズムを活用してマーケティングを行う際のポイント

医療ツーリズムの分野でマーケティングを行う際には、医療広告に関する法的規制を正しく理解し、適切な情報発信を行うことが重要です。
日本では「医療法」に基づき、医療機関や医療サービスの宣伝内容には明確な制限があり、広告で使える表現方法や使用できる媒体などが法律で細かく定められています。
以下に、代表例をまとめました。
| 区分 | 内容の例 | 広告の可否 |
| 基本情報 | 医療機関名・住所・診療科目・診療時間など、客観的に確認できる事実 | 広告可能 |
| 実績や効果 | 合理的な根拠なく「必ず治る」「他院より効果が高い」など、結果を保証・比較する表現 | 広告不可 |
| 体験談・口コミ | 患者の体験を通じて効果を強調する内容(SNS投稿やレビューを含む)※治療内容や効果に言及しないものであれば禁止の対象とならない。 | 原則として広告不可 |
参考:e-GOV「医療法」
このように、客観的な事実に基づく情報は認められる一方で、治療効果や優位性を示す表現は規制対象となります。
そのため、法律対応に精通した専門家や代行業者を活用し、法令遵守を前提にしたプロモーションを実施することを推奨します。
日本の医療ツーリズム×SNSの事例

日本の医療ツーリズムを海外に広めるうえで、SNSを活用した情報発信は有効です。特に外国人向けのプロモーションでは、写真や動画を通じて医療の魅力を視覚的に訴求することが重要とされています。
ここでは、実際にSNSを活用している事例として、美容医療や再生医療を対象とした訪日医療ツーリズム支援サービス「スーメイ(丝美)」を紹介します。このサービスは、株式会社クロスシーと株式会社KWINが共同で展開しています。
スーメイでは、KWINが保有する日本の医療機関に関する情報やこれまでの啓発活動をもとに、ショート動画SNS「RED(小紅書)」をはじめとする中国の主要インターネットプラットフォーム上で情報発信を行ってきました。
これにより、中国国内の潜在的な医療渡航希望者に対して、日本の医療サービスの魅力を効果的に届けています。
加えて、医療通訳資格を持つスタッフが在籍しており、来日前の情報提供から予約支援、受診時の同行までを一貫して対応可能です。
SNSでの広報と受診支援体制を組み合わせた取り組みは、日本の医療ツーリズム分野におけるSNS活用の先進的な事例といえるでしょう。
参考:株式会社クロスシー「訪日インバウンド向け医療ツーリズム支援サービス「スーメイ(丝美)」の開始のお知らせ」
日本の医療ツーリズムは中国人富裕層へのマーケティングに効果的

中国富裕層にとって、日本の医療は魅力的な選択肢となっています。
理由は、日本の医療が精密検査や先端技術の面で国際的に高い評価を受けており「安心・信頼・高品質」というイメージを持たれているからです。
近年、中国では健康志向が高まり、海外で質の高い医療を受けたいというニーズが拡大しました。特に以下の分野で日本の医療サービスへの関心が強まっています。
- 健康管理(人間ドック、がん検診などの定期健診)
- 美容医療(美容整形・皮膚治療・アンチエイジング)
- 長寿医療(予防医療・先端検査を含む)
このようなニーズに対して、効果的なプロモーションを行うためには、中国人富裕層の価値観に沿った訴求が必要です。
特に中国人は、仁保に量に対して「安心」「清潔」といった点を求める傾向にあるため、「日本で安心して治療や検診を受け、その後の滞在も快適に楽しめる」といった提案が、効果的な訴求につながります。
さらに、中国の富裕層は検索エンジンよりもSNSや口コミを重視する傾向があります。
WeChatやWeibo、RED(小紅書)などのSNSを活用し、実際の医療体験や滞在の様子を視覚的かつ体験的に発信することが、集客において効果的です。
日本企業が中国向けに医療ツーリズムの情報を発信するなら「東京マンダリンアワード」へ

日本の医療ツーリズムとは、海外の人が医療サービスを受けることを目的に日本へ渡航することを指し、治療だけでなく、健康診断や美容医療など多岐にわたる目的があります。
需要が拡大している背景には、日本の医療が誇る高度な技術、清潔で安全な環境、きめ細やかなホスピタリティが評価されていることが挙げられます。
なかでも近年は、中国で健康志向が高まり、質の高い海外医療への関心が急速に高まっており、日本の医療サービスに注目が集まっています。
こうした中国市場に向けて効果的にアプローチするには、SNSの活用が重要です。中国では、検索エンジンよりもWeChatやWeibo、RED NoteなどのSNSを通じた情報収集が主流であり、購買・訪問の意思決定にも大きな影響を与えます。
そのため、中国人富裕層の特性や行動傾向を理解し、それに合わせたSNS戦略を設計・運用することが欠かせません。
中国SNS運用代行のプロである「東京マンダリンアワード」なら、中国SNSのアカウント開設から戦略設計・投稿運用までの一括支援が可能です。
医療や不動産、観光業など幅広い業界でフォロワー獲得や予約増加の実績を持ち、中国人向けマーケティングの最適化を実現しています。
中国人富裕層へのアプローチを強化したい企業担当者の方は、まずは無料でお気軽にご相談ください。医療ジャンルは、中国の法律やSNSでも特に規制の厳しい領域になります。広告の準備はマーケティングのプロに相談しながら慎重に行いましょう。